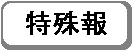
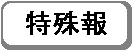
平成6年度病害虫発生予察特殊報(第2号)
奈良県病害虫防除所
1 病害虫名 ミカンキイロアザミウマ (学名:Frankliniella
occidentalis PERGANDE)
2 発生確認の経過
1)本種は北アメリカ原産で1990年に千葉県と埼玉県で発生が確認され、近畿では1994年に和歌山
県、大阪府で発生が確認されている。
2)平成6年12月下旬以降、県北部の施設栽培のバラで、防除困難なアザミウマの発生があり、地
域農業改良普及センターから病害虫防除所に診断依頼がなされた。現地調査を行った後、神戸植
物防疫所に種類確認の同定依頼を行ったところ、本県未発生のミカンキイロアザミウマであるこ
とが明らかとなった。
3)現在までの調査では発生は県北部の施設バラに限られているが、花き類を中心に今後の発生状況
に注意が必要である。
3 形態
雌成虫:体長1.4〜1.7mm、体色は明黄色〜褐色と変異が大きい。
雄成虫:体長1.0〜1.2mm、体色は明黄色。
本種は肉眼では、ミナミキイロアザミウマより大きく見える。また、ヒラズハナアザミウマに
よく似ている。
顕微鏡下では以下の特徴により他のアザミウマ類と区別する。
・前胸背板に5対の長刺毛がある。・・・図中4
・前翅前脈の刺毛列が途切れることなく一様である。・・・図中6
同じ属のヒラズハナアザミウマとの区別は
・複眼後方第4刺毛が特に長い。・・・図中2のC
・後胸背楯板に一対の鐘状感覚器がある。
4 生態及び被害
1)本種は卵から1齢幼虫、2齢幼虫、前蛹、蛹を経て成虫となる。
2)卵は葉や花弁などの組織内に1個ずつ産みつけられる。1雌成虫当たりの産卵数は150〜300個。
3)幼虫は花弁、新葉などに生息し、これらを吸汁加害する。2齢を経過した後、地表に移動し、土
中や、落葉中で蛹化する。
4)前蛹時期は自らは動かず、加害もしない。
5)成虫になると再び花弁、新芽、新葉に移動し、加害する。
6)1世代に要する期間は、15℃で約40日、20℃で約20日、27℃で約14日で、成虫の寿命は30〜45
日ある。発育零点が6.7℃と低く、野外での越冬も可能と考えられる。
7)本種による直接の被害は成幼虫の吸汁による被害である。被害部は変色したり、奇形が生じる。
特に花き類では、開花後に加害されると暗色花弁には白色条が、明色花弁には褐色条が生じ、商
品価値がなくなる。野菜類では花への寄生やトマト幼果の白ぶくれ症状がある。葉に寄生すると
白斑を生じる。また、海外では本種はトマト黄化えそウイルス(TSWV)のベクターと報告さ
れている。果樹では吸汁によってハウスミカンで果実表面が白っぽいかすり状となる。
5 寄主作物
寄主範囲は広く、50科200種に及んでいるが、主な寄主作物は以下の通りである。
・花き:バラ、キク、シクラメン、トルコギキョウ、ガーベラ、カーネーション、インパチェンスなど
・野菜:イチゴ、トマト、キュウリ、ナス、ピーマンなど
・果樹:ミカン(ハウス栽培)、ブドウ、モモなど
6 防除対策
1)苗による発生の拡大を防ぐため、未発生地では既発生地からの苗の持ち込みに注意する。
2)発生地では収穫後の被害作物が次の発生源となるので、速やかに処理する。特 にバラ栽培では番外花等、収穫しない花も全て除去し、施設内に残さないよう に処分する。
3)圃場や施設周辺の雑草などにも寄生するため、雑草を除去、処分する。
4)施設では本種の侵入、飛散防止のため開口部に寒冷紗などを設置する。
5)本種に登録のある薬剤、有効な薬剤は表にまとめた通りである。
ただし、本種と類似種のヒラズハナアザミウマやミナミキイロアザミウマとは有効な薬剤が異なるので、的確な防除のためにも、わかりにくいアザミウマや薬剤の効果に疑問がある場合には最寄りの農業改良普及センターや病害虫防除所まで連絡して下さい。